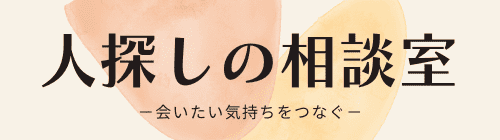相続の手続きが始まると、戸籍をたどって相続人を確定する作業が必要になります。ところが、「連絡の取れない親族」「何十年も音信不通の兄弟姉妹」など、所在不明の相続人がいることで手続きが止まってしまうケースは少なくありません。
相続は、相続人全員の合意がなければ進められない場面も多く、たとえ財産に関心がないような親族であっても、その所在を把握し、意思確認を取ることが重要になります。放置しておくと、遺産分割ができなかったり、裁判に発展するリスクもあります。
この記事では、相続手続きのために行方不明の親族を探す方法として、戸籍や住民票をたどる方法、専門家への依頼、探偵による調査、さらには法的な手続きまで、実務的な視点からわかりやすく解説していきます。
相続における「所在不明の親族」とは
相続手続きでは、亡くなった方の財産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」が必要です。原則として、法定相続人全員がこの協議に参加し、署名・押印を行わなければ正式な合意とは認められません。つまり、ひとりでも連絡のつかない相続人がいると、協議そのものが成立しないのです。
どういったケースで問題になるのか
とくに多いのは、兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)との関係が途絶えてしまっているケースです。親族付き合いが疎遠なまま何十年も経ち、どこに住んでいるのか、そもそも生きているのかさえわからない。そうした状態では、相続人であることは戸籍で確認できても、「同意書にサインをもらう」という実務的なステップが進められません。
家族関係が複雑な場合、相続人のなかに結婚や離婚、養子縁組などで名前が変わっていたり、戸籍が転々としていたりして、所在の特定に時間がかかることもあります。
所在不明が相続に与える影響
このような所在不明の相続人がいる場合、手続きの遅れだけでなく、相続財産の管理・処分に影響が出る可能性もあります。たとえば不動産の名義変更ができなかったり、預金の解約ができなかったりするなど、相続全体が宙に浮いたまま長期化してしまうのです。
一方で、法律上の相続放棄は家庭裁判所での申述が必要であり、黙って音信不通になっているだけでは放棄したとみなされません。したがって、所在がわからないからといって勝手に手続きを進めることはできず、まずは「その人がどこにいるのか」を確認する必要があるのです。
まずは戸籍と住民票でたどる
相続人の所在が不明な場合、まず最初に行うべきは「戸籍」と「住民票」の情報をもとに、その人物の足取りをたどることです。これらは、個人の過去と現在の所在地・身分関係を公的にたどるための最も基本的な手段であり、多くのケースで重要な手がかりとなります。
戸籍から追える情報とは
戸籍は、出生・結婚・離婚・死亡・転籍といった人生の節目を記録した公文書です。相続においては、「相続人であること」を確認するだけでなく、その人がいつ・どこに転籍したのか、現在どこの戸籍に属しているのかを確認する目的でも用いられます。
戸籍の取得は、原則として直系の親族など一定の関係がある人、または「正当な利害関係」がある人に限られます。相続手続きのために所在不明者を探す場合は、被相続人との関係性を示す除籍謄本などを添えて請求します。
戸籍の「筆頭者」や「本籍地」が変わっていれば、過去の戸籍をたどる必要があります。特に、結婚や離婚で姓が変わっていたり、転籍を繰り返している場合は、一通の戸籍だけでは足りず、複数の自治体をまたいで追跡調査が必要になることもあるため注意が必要です。
関連ページ:戸籍や住民票から人は探せる?個人でできる調査の範囲を解説
住民票・除票で現住所を確認する方法
戸籍から転籍の履歴がわかったら、次に必要なのは「住民票」の取得です。住民票には、現在の住所・世帯構成・転出入の履歴などが記載されており、対象者の生活実態を把握する上で非常に有用な情報源です。
ただし、住民票の取得には「正当な利害関係」があることが前提です。相続手続きの一環であることを証明するために、被相続人との関係を示す書類(戸籍謄本や遺言書など)を提出する必要があります。
もし対象者がすでに転出していたり、死亡している場合には「住民票除票」を取得することで、過去に登録されていた住所と転出先を確認できることがあります。除票の保存期間は原則5年ですが、自治体によってはそれ以上保存している場合もあるため、確認のうえで請求しましょう。
行政書士・司法書士への依頼も有効
戸籍や住民票の調査は、法的には個人で進めることも可能ですが、内容が複雑である場合や複数の自治体をまたぐ場合などは、行政書士や司法書士に依頼することで作業の効率と正確性が格段に高まります。
特に行政書士は、「職務上請求書」という制度を使って依頼者の代理で戸籍・住民票を取得することができます。依頼者が直接役所に出向くことなく、必要書類をそろえてくれるため、時間と労力を節約できます。
また、司法書士は不動産登記や相続登記に強く、所在不明の相続人が絡む登記の複雑な問題にも対応可能です。相続に関係する複数の手続きをまとめて相談できるため、全体の進行をスムーズにしたい場合には特に有効です。
それでも見つからない場合の選択肢
戸籍や住民票をたどっても行方がわからない。行政書士の手を借りても転出先が追えない。そうした場合、次に検討すべきは民間調査(探偵)や法的手段です。相続の手続きは待ってくれません。期限や他の相続人の状況も考慮しながら、次のステップを選ぶ必要があります。
探偵に依頼して現在の所在を調べる
相手の氏名・過去の住所・卒業校・勤務先・関係者など、ある程度の情報が揃っている場合には、探偵に調査を依頼することで現在の所在地が判明する可能性があります。特に戸籍で追えない範囲(転居後の足取りや人間関係)に強いのが探偵の特徴です。
探偵が行う調査は、主に聞き込み・記録調査・張り込みなどを組み合わせた実地型。調査対象が一般人である以上、合法の範囲で慎重に行動されます。費用は調査期間や手がかりの量によって異なりますが、10万〜50万円程度が相場とされます。
所在不明の相続人が見つかりさえすれば、分割協議書の作成や意志確認が一気に前進するため、コストパフォーマンスとしては高いと感じる人も多いです。
関連ページ:人探しの調査にかかる費用は?相場と内訳を解説
失踪宣告や不在者財産管理人の申立て
どうしても見つからない、あるいは連絡が取れたとしても協議に応じない場合の選択肢となるのが、家庭裁判所での法的手続きです。
1つ目は、不在者財産管理人の選任申立てです。これは、行方不明者の代わりに財産管理を行う人を選任してもらう制度で、相続手続きを進めるために活用されます。裁判所が認めれば、協議や財産の処分などをその代理人が代行できます。
2つ目は、失踪宣告です。こちらは7年以上行方不明の場合に限り、法律上その人を死亡とみなす制度です。これにより相続が正式に発生し、他の相続人で手続きを進めることが可能になります。ただし、失踪宣告はハードルが高く、家庭裁判所の審理にも長期間を要するため、緊急時の選択肢とは言えません。
調査にかかる時間と全体の見通し
所在不明の親族を探す作業は、相続人確定という土台を整える極めて重要な工程です。とはいえ、戸籍調査に1〜2週間、住民票除票での追跡にさらに数週間、探偵による調査が加われば1〜2ヶ月かかることも珍しくありません。
相続税の申告期限(通常、相続発生から10ヶ月)や不動産処理のスケジュールなどもあるため、早めに行動し、必要に応じて専門家や調査会社を活用することが賢明です。
所在不明の親族が見つかった後の対応
戸籍や住民票、探偵調査などの手段を経て、ようやく所在不明だった相続人が見つかった場合、相続手続きは大きく前進します。ただし、見つかったからといってすぐに解決するとは限らず、相続人が協力的かどうかによって、その後の対応は大きく異なります。
協議・同意が得られた場合
相続人が協議に応じる意思を持っていた場合、最初にすべきことは遺産分割協議書への署名・押印を依頼することです。その際には、本人確認書類(免許証やマイナンバーカードの写し)や、印鑑登録証明書の添付が求められます。
特に遠方に住んでいる場合などは、書類を郵送でやりとりすることもあります。分割内容に合意が得られれば、協議書を整えて、預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続手続きを進めることが可能になります。
なお、相手が遺産を放棄したいという意思を示している場合でも、正式に「相続放棄」の申述をしなければ、放棄したと見なされません。家庭裁判所での手続きを促す必要があります。
見つかっても同意が得られない場合
連絡が取れたものの、相続人が協議に応じない、署名を拒否する、連絡自体を断ってくるといったケースもあります。こうした場合は、家庭裁判所での「遺産分割調停」へと進む必要があります。
調停では裁判所を介して話し合いが行われ、それでも合意に至らなければ、最終的に「審判」によって裁判所が分割内容を決定します。調停や審判の場では、不公平がないよう法定相続分を基本に判断されるため、冷静な対応が求められます。
また、相続人の一部に遺産を取得させたくないときや、協議が極端に難航する場合には、「代償分割(他の相続人が金銭を支払って遺産を取得)」や「換価分割(財産を売却して分配)」といった方法を選択することも検討されます。
まとめ
相続の場面で親族の所在が不明になると、手続き全体がストップしてしまうことがあります。しかし、戸籍や住民票をたどることで多くのケースは対応可能であり、早めの確認と情報整理が、相続トラブルの回避につながります。
どうしても発見が難しい場合には、探偵など民間調査の利用や、不在者財産管理人・失踪宣告といった法的措置を視野に入れることが重要です。いずれにしても、「そのうちなんとかなる」と放置してしまうと、相続税申告や財産管理の期限に間に合わないリスクもあります。
早期に行動を起こし、必要であれば専門家や第三者の力を借りながら、円滑な相続の実現に向けて一歩ずつ進めていきましょう。